AAAゲーム(大作ゲーム)の開発予算が年々高騰し続け、12万円のプレミアムなアップグレード・コンソールが登場し、コンソールゲーム業界はこれからどうなっていくのか? 莫大な開発予算に対してどう対抗するのか? ビデオゲームは今後どう変わっていくのか? そして、私たちがプレイするゲーム機というハードウェアは、その大部分においてもう重要ではない、というところまで来ているのでしょうか? プレイステーション・ワールドワイド・スタジオの前会長であるショーン・レイデン氏がユーロゲーマーのインタビューで語っています。
ショーン・レイデン氏がまず危惧しているのは、AAAゲームの開発費が数億ドルレベル(数100億円)にまで高騰した事によって、新たな新規IPを生み出すリスクが大きくなってしまい、逆にヒットした続編、リマスターなど安易な方向に行ってしまう事で、多くの模倣、続編が生まれ、範囲が狭くなってしまう事で、ハイエンドのクリエイティビティがしぼんでしまうのが問題だと述べています。
そしてオンラインの普及に伴う弊害も指摘しています。
“PS1やPS2では、1台のハードで約25本のゲームが売れました。PS3やPS4では、人々がオンラインに常時接続することによるネットワーク効果によって、その数はかなり少なくなってきています。一度オンラインの世界に入ったら、オンラインの友人と離れることはないのです。私には息子がいますが、彼のマシンからFIFAが離れることはないだろうと思います。彼のPS5には永久にFIFAが埋め込まれていると思う。他には『フォートナイト』や『ウォーゾーン』のラビットホール(本来の目的から逸れてしまい、そのままそこから中々抜け出すことが出来なくなる状況に陥ること)にハマると、もう他のゲームはあまりしなくなるのです。ですので、ユーザーがそれによって視野が狭まっている事が心配です。”
これはよく分かる意見ですね。特定のゲームにハマるとその世界に居続けるのが快適になり、中々次の新しいゲームに移行出来ない事がたまにあります。
これにオンラインのフレンドが絡んでくると尚更で、コミュニケーションも絡んでくるので、それが日常と化してしまうと、正にラビットホール=ウサギの穴と化します。これが原因で、以前のように1台あたりのゲームソフトの売り上げ(アタッチレート)が低下しているという副作用が発生しているようです。これも没入感の向上による弊害ですね。
最近は、コンソール世代が時間の経過とともに成長していないことも議論されています。フィル・スペンサー氏も述べていますが、コンソール市場が頭打ちになりつつある懸念が指摘されている事について、レイデン氏は
“SEGAサターンやニンテンドー64、PS2、Xboxの時代など、PS1の時代にあったすべてのものを積み重ねて見てみると、どの世代もハードウェアの総計では、2億5000万台を超えていないようです。
一度だけ爆発的に売れたのは、『Wii Fit』が発売されたときで、任天堂の『Wii』を買えば痩せられると思った人が大勢いました。クリスマスの一瞬、「ああ、痩せよう」ということで、ゲーム機の販売台数が伸びましたが、その後はまた落ち込みました。
新型コロウィルスによるパンデミック(世界的感染拡大)の間に、ゲームの収益が23%増加したと言われても、それは必ずしも新規参入によるものではありません。
これは、私が開発者やパブリッシャーと会うときに話す存亡の危機です。私たちは次の世代を育てていないのです。私たちは次世代をTikTokに奪われているのです。ゲームの競争相手はXboxでも任天堂でもない。 ゲーム活動から時間を奪うことができる、異常な時代の流れにある他のすべてなのです。私たちは、業界としてその脅威に正面から向き合っていないのではないでしょうか。
対応策として具体的に2つか3つのことに取り組む必要があります。ひとつは、ゲーム開発費の爆発的な高騰です。世代が進むごとに、ゲームを作るコストは2倍になっています。PS1で100万ドルかかったものが、2倍、4倍、16倍となる。指数関数的に増えていくのです。私が最後に関わったPS4世代では、ゲーム開発費はトップクラスになろうと思えば1億5,000万ドルで、これはマーケティング前の話です。その計算では、PS5のゲーム開発費は最終的に3億ドル(450億円)から4億ドル(600億円)に達するはずで、これは到底持続可能なものではありません。
480pのレンダリングはそれほど高価ではありませんでしたが、4K 60fpsとなると、かなりの人数と時間、予算が必要になります。私たちがフォト・リアリズムに執着し、不気味の谷(リアルさが増して一定レベルを超えると、逆に違和感、嫌悪感、怖さを感じてしまう事。)を追い求めていることを見てみましょう。 私が見たところ、不気味の谷は越えられないと思いますし、それを追い求めるべきではないと思います。
PS1では、ゲームの中で通りを歩いている建物のすべてのドアを開けられないことでした。 今は、すべての家に入り、すべての引き出しを開け、すべてが破壊可能であることが期待されています。それはリアルで素晴らしいことですが、それを実現するには相当なお金がかかります。その点を考慮しなければなりません。
開発費の高騰で逆に新規大型タイトルへのリスクが増すことで、安全なヒット作の続編、リマスター、リメイクが増えるという事になり、幅が狭まっているという、、確かに最近でもCONCORDが記憶に新しいですが、新規大型タイトルを避ける傾向に陥ってしまう状況になりつつあるのかもしれませんね。
プレイしたプレイヤー総数の50%しかゲームの最後を見られないとしたら、最終レベルに何百万ドルも費やして、半分の人しか見る事が出来ないというのはどうでしょうか?
巨大なゲーム体験を作るために多くの資金が投入されているのに、多くのプレイした人々はそれを見ていないのです。私は、より多くの人々がゲームを最後までクリア出るようなムーブメントを望んでいます。
これも一理ありますね。ゲームをクリアすると、実績解除しゲームをプレイしたプレイヤーの何%がクリアしたのかが分かりますが、ゲームを終わらせた際の実績を見ると、本当にゲームをプレイした内の50%に満たない人しかクリアしていない事が分かります。YOUTUBEの影響も少なからずあるかもしれませんね。見ただけでプレイした気になってしまうような人もいるらしいので、そういった弊害もありそうです。
これは発売から数年経過したゲームを遅れてクリアした時も似たような数字でした。良くも悪くもゲーマーも上級者とエントリー層と二極化しているのかもしれません。増して、やり込んだ際に解除される実績となると、クリアしたプレイヤーは数%程度しかいません。いかに多くのプレイヤーがそれほどやり込めていないのかが分かります。
では、どうすればいいのか? その答えのひとつは、単純に聞こえるかもしれないが、ゲームが長すぎることだと思います。
私は『レッド・デッド・リデンプション2』をまだプレイしていません。引退した私には90時間もゲームをする時間はありません。長い間、私たちは『100時間のゲームプレイ』を追求し続けていました。これはすごいことになる。100時間のゲームプレイだ!』ってね。それが最も重要なことのように。
これは、平均的なゲーマー世代が18歳から23歳だった初期の頃の指標です。18歳から23歳というのは、時間が豊かでお金がない。しかし、ゲーマーの平均年齢が20代後半、30代前半と上がるにつれて、その逆になっていくのです。お金にはある程度あるが、時間には不自由する。ですから、私たちの現在のアプローチは市場や現実にミスマッチしていると思います。
私は80時間、90時間のゲームを何本も作ってきた。最初に言っておくが、それらは必ずしも100%質の高い時間ではなかった。また同じフィールドを走っているのか、、と感じる瞬間がたくさんありました。
18時間から23時間のゲームプレイを取り戻せるような、しかしコントローラーを置きたくなくなるような魅力的なゲームプレイができる世界を見てみたいですね。
ゲーム全体が、『バイオハザード』で突如犬が窓から飛び込んできて、恐怖のあまりコントローラーを落としてしまう瞬間のようであってほしいのです。規模や範囲を縮小できるなら、そういうゲームの瞬間をもっと増やしたいですね。
結局、当時20〜30代だったユーザーが歳を重ねて今に至っている事でユーザー数があまり変わらない状況なんでしょうかね?w
もちろん、新しい世代のゲーマーも多少は増えているでしょうけど、結果的に頭打ちになっている事からすると、歳を重ねたゲーマーの中にはゲームをやめた人もいるでしょうし、プラスマイナスでそういうことになっているのかもしれませんね。
そしてゲームが長すぎるという問題、短すぎれば短い、ボリューム不足と批判され、価格が高いとフルプライスなのに短いと言われる。しかし、開発費は高騰、価格は上げざるを得ない。
相次ぐ、スタジオ閉鎖、開発タイトルの中止、サービス中止など、多く起きている事からも、開発スタジオ、プラットフォーマーも難しい選択を迫られている状況なのかもしれません。
レイデン氏は、他にもマイクロソフトのフィル・スペンサーさんと同様に
“PS1からPS2、PS3からPS4程の世代間の飛躍が無くなってきている。率直に言って、一部のマニアしか違いが分からない領域まで来ている。PS1からPS2の頃のような飛躍的な性能ジャンプはもう見られないでしょう。
テラフロップスやレイトレーシングの話をしているのであれば、すでに多くの人が理解できる範囲を超えています。私たちは今、ハードウェアの技術革新曲線が頭打ちになりつつある地点にいます。
同時に、シリコンのコモディティ化(独自性やブランド力によって差別化されていた商品が、類似商品の出現によって、一般的な商品になること)によって、Xboxやプレイステーションを開けてみると、ほとんど同じチップセットになっている。 すべてAMDが製造しているのです。
各社は独自のOSや独自の「秘伝のソース」を持ってはいますが、本質的には同じものです。 コンソールのあり方については、最終的な仕様にかなり近づいていると思います。
本当の競争はコンテンツにあります。パブリッシャーにとっては、どのハードウェアを支持するかではなく、コンテンツこそが競争相手となるべきです。
次の世代とまではいかなくても、間違いなく次の次の世代には、コンソールは無用の長物になっていると思います。”
と述べています。
マイクロソフトがコンソール市場の頭打ちで成長の限界を感じ、ゲームパスとクラウドゲーミングをゲートにモバイルユーザーを自社サービスに取り入れる事にフォーカスしているというのは、ある意味に理に適っているなと納得です。
今の時代、コンソール中心という考えは過去の物となりつつあるのかもしれません。
もしかすると、10年後にはコンソールという概念は無くなっているかもしれませんね。
レイデン氏はソニーが角川の買収について、両社の関係は長く親密であることを認め、以前角川の役員だった方々が現在ソニーにいることなども明かしていますが、エルデンリング2に関しては知らないとの事。
他にもレイデン氏はインタビューで様々な事について語っており必見の内容となっています。
🔚
via ユーロゲーマー




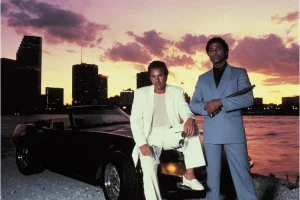












コメントを残す